「文化人類学」という学問を聞いたことがあるひとは、どれくらいいるだろう。大学で文化人類学専攻だったわたしだが、同じ大学の人にすら「え、何ですかそれ」と聞かれることも多かった。
だから何かの拍子に文化人類学の話題が出ると、逆に驚いてしまう。「え、文化人類学知ってくださっているんですか!?」と心の中で叫んでしまうくらい。
ここ数年は一般の方にも広く知られる文化人類学の著書もずいぶんと出ている。まだまだマイナーな学問だとは思うのだが、もしかしたら皆さんが知っている本もあるかもしれない。
代表的なものが上橋菜穂子さんの『鹿の王』や『精霊の守り人』、『獣の奏者』だろう。学術的な作品ではないが、文化人類学者である上橋さんの視点が存分に活かされた素晴らしい小説だ。
ご存知の方もいるかもしれないが、上橋さんはオーストラリアの先住民アボリジニを研究なさっている、れっきとした文化人類学者だ。ちなみにこの3月には新作の『香君』が発表される。楽しみすぎて眠れない……!
* * *
……閑話休題。文化人類学の学術寄りの本について続けよう。
わたしたちはどうしてこんな気持ちになってしまうのか?──そんな素朴な問いに経済や感情、国家の仕組みを紐解きながら答える『うしろめたさの人類学』(松村圭一郎/2017)。

*
「こんな経済あり!?」と思わず叫びたくなる内容が満載の『チョンキンマンションのボスは知っている』(小川さやか/2019)。著者が香港在住のタンザニア人ビジネスマンに長く密着取材した渾身の一冊だ。

この2冊は今も書店で見かけることが多い。
* *
他にも、味噌、醤油、ヨーグルト、日本酒、ワインなど、世界中にある発酵食品に魅せられた著者が世界を旅して書き記した『発酵文化人類学』(小倉ヒラク/2020)。
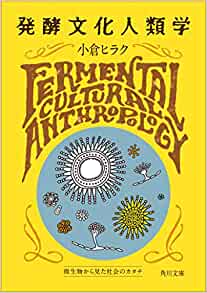
*
犬や馬をパートナーとする動物性愛者「ズー」について描いた『聖なるズー』(濱野ちひろ/2019)。性暴力に苦しんだ経験を持つ著者が、彼らと寝食をともにしながら、人間にとって愛とは何か、暴力とは何か、考察を重ねた本だ。

*
海外で言えば、『負債論──貨幣と暴力の5000年』(邦訳は2016年)や『ブルシット・ジョブ──クソどうでもいい仕事の理論』(邦訳は2020年)を記したデヴィッド・グレーバーも人類学者だ。(2020年に59歳でグレーバーが急逝したというニュースを聞いたときはなかなかにショックだった)


*
「あれも文化人類学だったのか!ちょっとおもしろいかも」
「あれもこれも文化人類学……?結局何やってるか意味不明……」
色々な感想を抱かれがちな学問だけれど、文化人類学に「沼落ち」してしまった奇特な人間として、今回の記事ではその魅力をたっぷりとご紹介させていただきたい。


