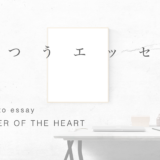水曜日。彼女と会い、お気に入りの定食屋さんへ連れ立った。大きなれんこんのはさみ揚げを箸で割りながら、彼女は朗らかに言った。
「身体をあたためて、しっかり養生してれば治るから大丈夫。無理しないでね」
「ありがとう。なんかね、私のことだから、ほら、いつもみたいに考えが飛躍しちゃって。女のつらさについて考えちゃったりしたんだ。妊娠がどうとか、結婚がどうとか。そういうのって、私たちの身体に頼ってる部分が少なからずあるじゃない」
「そうだね」
うん、うん、と彼女は食事を口に運びながら言う。
「そう考えちゃうのも仕方ないよ。実際、私だって最近結婚して、このまま仕事のキャリア積んでいくか、子ども産んで家庭を持つか、すごく悩んでるし」
「そういう歳だよね、もう」
でもさ、と彼女は言った。私の好きな切れ長の瞼の端に、今日もきれいなアイシャドウが乗っていた。
「それは、自分で決めることだから。自分の人生だもん。
私はどんな選択をした人であれ尊重したいよ。それに、女は自分が思っている以上に強いからね」
弱っても、大丈夫。焦らなくて大丈夫。
澄んだ黒い瞳が私を見る。形の良い唇がほほ笑む。ああ、彼女は強い人だな、と思った。いつまでも私の憧れであり、同じ時代を歩んできた戦友でもある彼女の凛とした佇まいが愛おしくなった。
私もいつか、あなたみたいに生きられるようになりたい。強く、まっすぐ前を向いて生きられるように。
「あ、そうだ」
ふと、彼女が椅子に置いたバッグに手を差し入れる。店のドアから漏れる光が、彼女のつややかな髪を透かしていた。
「具合悪いって聞いてたから、これ。
ウォームベアっていって、中に入ってるカイロをあっためて使うの。
私も仕事で疲れた時、目もとや手首に使ってるんだけど、これが案外癒されるのよね。
よかったら使って」
*
渡された透明の箱には、ぽってりとした白いふわふわのテディベアがいた。
箱から取り出し、触れてみる。幼い頃、どこに行くにも一緒だったきつねのぬいぐるみを思い出した。優しく、やわらかな手触りだった。
「ありがとう。
今、結構弱ってたから、こういうのすごく嬉しい。
大切に使うね」
両手に抱き、ゆっくりと箱に戻す。これは私にとって特別になる、という予感が胸をあたたかく射抜いた。その予感ごと抱きしめながら彼女と別れ、家に帰ってすぐにぬいぐるみを温め、まだなお針を刺したようにひっそりと痛む下腹部へとあてがった。