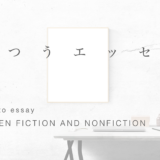私の使っているキヤノンの一眼レフには、シンジという名前が付いている。昔、一時的であっても感情のゆれを共有出来た芸大の男友達の名前だ。
私達は互いの部屋に通い、夜な夜な自分達の好きなアーティストの話や、感性に触れた芸術の話を缶ビール片手に語り合った。ジム・ジャームッシュの映画を観て、このシーンの静寂には意味がある、という話だけで夜を明かしたこともあった。開放的になる気持ちよさを味わえたのは、これが初めてだった。
そのひと時というのはどこか不整合でありながら、当時の私には、これが有りさえすれば他を失っても構わない、と思うほどの、重みと愉しみの交ざり合った時間だった。芸大に入学したのは、世論を斜め上から俯瞰して感じたことを表現したいというある種、私の人間としての“癖”だった。故に、いつも周りで起きた事象についてシンジと持論を展開していた。悲しい、虚しい──世の中で起こるほとんどに悲観をし、共感を求めた。そうすることで、味方を作ろうとしていたのだと思う。彼との時間は、生きることの煩わしさから目を背けて身を任せるのに最も適していた。
しかし時を同じくして、私は誰かと共に時間を過ごすことで大きく深くなっていく孤独の渦に飲み込まれ、精神を病んだ。孤独というのは、他人といることでよりいっそう真実味と所在が増していく。その孤独感は早朝、時には真夜中、家まで映画を観に来たシンジを駅まで見送り、ホームから電車が去った瞬間に訪れた。夜明けまで一緒にいた日には、これから仕事に行くサラリーマンの横で真新しい陽の光に照らされたホームに立ち尽くしていると、言いようのない寂しさにうずくまりそうになることもあった。大学でも授業中に気がそぞろな日々が続き、単位を落として留年し、その間に彼は器用に単位を取り続け大学を卒業した。