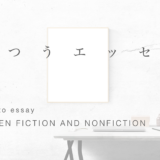桜の花びらがベランダに舞い込む頃、彼から連絡をもらった。大手の商社に就職するという。これから忙しくなるけど、一緒に映画を観たり語り合った日を忘れない、と。それは事実上の別れの言葉だった。なぜ、と私は大学という自由の檻に囚われながら憤った。なぜそんなにも不釣合いな、誰も貴方の“本当”を理解してくれないような場所に、あなたは行ってしまったのか。
疑問が晴れないまま二人の距離は遠ざかり、ついに連絡も途絶え、私達は元の他人に戻っていった。私の病状は治らないどころか、更に悪化の一途を辿っていった。心療内科に通い続け、教授に頭を下げながらなんとか単位を取り、大学を卒業。一度はクリエイティブな方面に進んだけれど、人間関係の問題に直面し、またも精神的な傷を負い、徐々に休職へと追いやられていった。あの頃の彼は正しい道を歩んだのだと、もうどこにも彼と繋がるツールが無くなった後に気付いた。
今の私は休職、というモラトリアムを始めてちょうど一年になる。道端に咲いている花や雨が降った日のアスファルトに反射する光が美しいと感じるようになり、世界がほんの少しだけ、鮮やかに見え始めた。自分の半身のように抱えていたカメラで写真を撮りだしたのは、そんな理由からだった。一秒ごとに変わっていく世界を見逃したくなかった。誰に見向きもされようとも、自分の感性を信じたかった。信じて生きていきたかった。
私だけがまだ、恋人にも友達にもなりきれなかった男の名前をカメラに付けて、そのカメラが瞬きするのを喜んでいる。彼が好きなものを語るとき、しきりに瞬きする癖があったことを思い出して、今日もカメラを世界に向ける。
休職し始めの頃、私はよしもとばななの本ばかりを読み漁った。心がなぐさみを求めていたのかも知れない。彼女の物語はいつだって優しい。それも手放しに優しいのではなく、ちゃんと現実味を帯びての優しさで、私にはそれが丁度良かった。
最初は『キッチン』。それから『白河夜船』、『ハゴロモ』。白い綿のおくるみに包まれている赤ちゃんのような気分で、毎日本を読み、毎日写真を撮った。押入れから幼い頃に使っていた“ねんね” ──寝る時に敷いていたライナスの毛布のようなもの──を引っ張り出して、昼の揺蕩う光の中で撮ってみたりした。