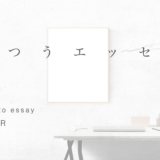愛について語ろうか、というテーマでエッセイを書かないか、というときに僕の頭に最初に浮かんだのは、キルギスでのこのエピソードだった。
「愛情は誰にでもあるものだから」という善良で、それゆえに乱暴な言葉を、8年経った今でも僕は素直に受け取ることはできていない。愛情というものがよくわからないと思っているし、自分にフィットしているような感覚は依然としてない。
しかし、月日は人を変えるものだ(これは過去の偉人たちがどこかで言ってくれているはず)。
僕は愛情にさわれるようになった。さわってもいいかなと思えるようになった、といった方が正確かもしれない。
昔、小さい動物園で実施している「モルモットふれあいコーナー」に行ったことがある。動物が苦手な僕は恐る恐る膝の上にモルモットをのせた。膝の上でじっとしているモルモット。とまどって同じくらいじっとしている僕。どうすればいいか、よくわからない。モルモットの重さとあたたかさを感じる。少し慣れてくる。不快ではない。少し親密さも感じている。でも、相変わらずじっとしているしかない。お互いに。
僕にとっての愛情はモルモットのようなものだ。わからなくて、あたたかくて、重くて、近くて、遠い。なでたいような、なでたくないような。居心地がよいような、わるいような。動いてほしいような、じっとしててほしいような。
僕が愛情にさわれるようになれたのは、この8年間で僕に愛情を含めたさまざまな気持ちを届けてくれた人たちがいたからだ。それらは花のように香り、水のように満たし、陽の光のように僕をあたためた。それだけのことをしてもらえば、僕のような人間だって変わる。月日が人を変えるのではなく、人が人を変えるのだ。僕はそのうちモルモットを抱き上げることもできるようになるのかもしれない。一緒に暮らすところはイメージできないけれど。
偉人でない僕のエッセイが後世まで残ることはない。誰の人生にも影響を与えることはない。生成AIのデータセットの一部としてしか人類に貢献することはできない。それでも、キルギスで出会った戸惑いに対して何らか対応することは僕の人生にとって意義がある。
ということで、あと3回、もろもろ書いていこうと思う。
──