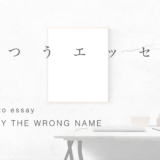「〜気がする」という表現を、つい使ってしまう。
テキストを書くときには「〜思う」といった推量表現を避け、なるべく断定で言い切ることがセオリーとされている。それは「読み手」に配慮するためだ。
*
テキストには「書き手」と「読み手」がいる。
「書き手」の立場からすると、何かを断定するというのは勇気が要る。あらゆることが「そこまでは言い切れない」からだ。エクスキューズとして、何かしらの推量表現を多用してしまうのだろう。
僕もぼんやりとテキストを打っていると「〜だろう」「〜思う」「〜ではないか」「〜気がする」といった表現ばかりになる。慌てて書いたテキストを振り返り、ここは断定でも構わないかなと推敲を重ねる。
余談だが、日本人は英語を発声するとき「I think〜」の表現が多いらしい。「日本人は考察が好きなんですね」と皮肉を言われた……そんな嘘かまこと分からないエピソードを聞いたことがある。なかなか日本人の国民性を象徴するようなエピソードだと感心する。
本題に戻ろう。
一方で、「読み手」の立場からすると、冗長表現は「無駄」にうつる。頭の中で整理しながら文章を読むにあたり、冗長表現は邪魔になるからだ。よほど名の知れた作家でない限り、「書き手」のテキストはじっくり読まれない。細かいニュアンスは重要でなく、冗長表現はすべからく切り捨てられてしまう。
そんな「書き手」と「読み手」のギャップは、いかんともし難いほど隔たれている。
だが多くの文章術のような「私見」では、「読み手」の立場のみ考慮されているようだ。
時間やお金という「コスト」を支払ってテキストを読んで「くれて」いるのだ。読んで「いただいて」いるのであれば、「読み手」が読みやすいと感じるようなテキストを書かなければならない。
たしかに、それは一理ある。
だけど、僕は安易に「読み手」の合理性に迎合するのは危険だと考えている。正しく意図が伝わらないという意味もあるが、「読み手」を信頼しない(=バカにする)ような態度は見透かされてしまうからだ。
僕は「読み手」を信頼したい。
小難しいテキストを編集することがある。「読み手」の合理性に配慮するのであれば、徹底的に赤入れして、ページ割りも考えて、過剰な形容詞や副詞を排した方が良い。だが、それは本当に「読み手」の「読みたい」という想いに応えているだろうか。
読み手は、同じような分かりやすい文章ばかりを読みたいわけではない。
様々な読み手がいるだろう。彼らは「面白い」文章を読みたいと考えているはずだ。たとえゴツゴツしていようとも、書き手の文体がそうであるならば、それを踏まえて読もうとするはずだ。
もちろん、何の配慮も施さないというわけではない。「読み手」を信頼するからこそ、むしろ徹底的に赤入れをして、「書き手」の特徴が際立つようなテキストを、編集者である僕は努めようとしている。
「ちょっと、『〜気がする』が多いような気がします!」
なんて、「書き手」に対してフィードバックする。それは「書き手」の文章が、いまよりも0.0001%でも面白くなるように、微力ながら苦心している証拠なのだ。