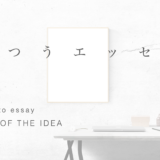ゴールデンウィーク、実家に帰る。
といっても、都内から普通列車で2時間もかからない。何なら4月にも帰っているから、イベント感がない。それでも「孫が来る」ということで、父も母も張り切っている。
張り切っている父と母がいるというのは、当たり前のようだけど、当たり前ではない。
親しい友人のうち、何人かは父や母を亡くしている。そもそも父母と良好な関係にない人もいるわけで。冒頭のような記述は、平凡なようで、誰かを傷つける可能性のある言葉だ。
そのような自覚は常に持っておきたい。
*
若干暗いトーンでスタートしたが、話を本題に戻す。(本題というほど、大それた話をするわけではないが)
実家に戻ると、僕がかつて所有していた本と向き合う。いつものことのように、本棚を前に、あれやこれや本を眺める。気分が向けば、そのうちの1冊を手に取って暇を潰す。(家からも数冊の本を持参しているので、そういうことは滅多にないけれど)
「かつて所有していた」と書いたが、いまも変わらず所有者は僕だ。
でも、実家の本棚に並ぶ本たちは、少しだけ他人行儀に見える。すでに誰かの手に渡ってしまったような、距離がある感じだ。
内容を忘れてしまった本も多い。だけど、不思議と、いつ読んだのかは憶えている。
1年前、3年前、5年前、10年前、20年前……。
何かに、誰かに傾倒し、他のことが目に入らなくなることもあった。そんな出会いのあった本は、僕のことを見て、「あんな風に思っていたこと、おいらは忘れてないからね」と意地悪な視線を送ってくる。
仕方ないじゃないか。あの頃は、今にも増して無知だったのだから。
なんで、こんな本を買ってしまったのだろうという本もある。けれど、そこに深く後悔はしないようにしている。その本を買わなかったら、いまの僕はない。自分に対する失望を踏み台にして、少しずつ版を重ねるごとに、僕という人間の中身をアップデートするのだ。
どれだけ誇れるアップデートになっているかは分からないが、かつての自分との差分を感じながら、苦々しい気持ちを噛み締める。
でも、それは変化してきたという証なのだ。これからも、きっと変化していくだろう。いまの自分を失望するような時期が、この先きっと来るのだろう。
そう考えたら、未来は、きっと希望しかないとも言えそうだ。