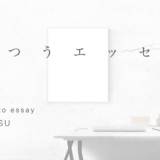エッセイの標準的な長さとは、どれくらいなのだろう?
……例えば、冒頭にそんな問いだけ残してエッセイを終えたとしたら、さすがにエッセイとして成立したとは言い難いだろう。起承転結ではないけれど、話の種が芽吹き、それが継がれ、急な変化が訪れつつ、最終的に結ばれる。そんなセオリーを、読み手は無意識で期待している。
いちおう、ここまでが「起」だけれど、例えばこの文章を書いている僕が、めちゃくちゃ眠いとする。それで「もうエッセイを書くのを止めたい」と思ったとする。「ふつうごと」を運営しているのは株式会社TOITOITOであり、その代表は僕だから、僕の責任下で書くのを止めることはできなくない。ちょっとくらいサボったってバチは当たらないよなと、先月諏訪大社で祈祷してきたばかりだし、その神さまに「すみません、今日はちょっと無理です」と謝れば、少ない減点で済ませてもらえるんじゃないかとも思う。ザ・希望的観測、というか、こういうときに限って「バチが当たる」といった表現を持ち出すのが狡いところだなあと思ったりするけれど、それはそうと、駄文を綴っていくうちに原稿用紙1枚の分量は超えることができた。
こうなると、そろそろ、どこで着地しようかを考えることになる。
ノープランで綴ってきたわけだから、結論めいたことも思い当たらない。バチも当たらないけれど、正解も思い当たらない。「エッセイの標準的な長さとは、どれくらいなのだろう?」と始めたわけだから、「そんなのケース・バイ・ケースですよ」という着地も考えられるが、それはいくらなんでも、つまらない。
つまらないは、詰まらないと書く。
つまり(詰まり?)、間が空きすぎているということだ。2000年代の漫才は、マシンガントークよろしく小ネタの連発で、お客さんを笑わせ続けることが主流だった。ラーメンズ、ルート33、ますだおかだといった例外はいたけれど、ハリガネロック、アンタッチャブル、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、ナイツ、NON STYLE、パンクブーブー。とにかく「何もない」時間を徹底的にボケで埋め、時間をギュッと詰め込んだのだ。
旨味をギュギュギュギュギュッ!と詰め込んだ加工食品のように、機能的なエッセイはカジュアルで外れがない。論旨も明快で、読んでいて納得感もある。
だが、「これって良く分かんねえなあ」という感覚も、僕はときどき無性に欲する。詰まらないエッセイで、どこか間が抜けて、でも、何度か読むうちに「ああ、こういうことか」と腑に落ちたりするような。
世の中、プロっぽいエッセイが多い。
プロのエッセイストのエッセイを読んで、それっぽい形に仕上げている。その能力に長けていることは、純粋に素晴らしいことだと思うけれど、僕が好むエッセイは、「蕎麦屋のラーメン」のように、あまりプロっぽくない邪道だったりする。
長さはどうだって良い。王道が幅を利かせるこの社会で、堂々と邪道を突き進むようなエッセイが、僕は好きだ。好きだった。今はどうだろうか。案外、王道なエッセイを欲しているかもしれない。
ああ、人間ってわがままだ。だから、エッセイは人間に合わせず、文章を自由にとことん遊ばせておけば良いのかもしれない。