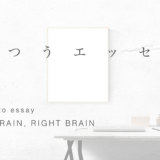建築家・隈研吾さんが提唱する「負ける建築」。自著のタイトルにもなっているが、建築を「勝ち負け」に擬えたことに対して妙に納得してしまった。
要するに、それまでずっとマジョリティとして君臨してきた高層ビル。高ければ高い方が良い、壮大であれば壮大な方が良いという価値観だった時代。自然と人工物の対比すら意識されていなかったときに、建築とは、あらゆる物質の頂点にたつような存在だった。(のだと思う)
隈さんは東京での仕事を一時干されたことがあったそうだ。地方の低予算の仕事にしか携われなくなったが、その土地にあるものに本質的な価値を見出し、自然と共存するような建築物を作るようになった。都心の高層ビルの「勝ち」的な価値観と対比して、「負け」る建築として位置づけたのだった。
*
たとえば6人が走る徒競走。1位になった人が「勝ち」であり、2位以下の人たちは「負け」である。同じように、世の中には「勝ち」よりも「負け」の人の方が多いというわけだ。(定義や基準にもよるが)
そう考えたときに、僕は全ての事象に対して「負ける」ことこそが自然な姿のように思えるようになった。
負ける組織
負ける出版社
負けるメディア
負けるコーヒーショップ
負けるランナー
負けるクリエイティブ
負ける起業家
あらゆる対象に「負ける」をつけることで、それは他者との共存を示唆する言葉になっていく。「勝ち」でなく「負け」であることで、共存よりも、もう一歩後ろに下がったような謙虚さも感じさせる。
「勝つ」とは孤高なものだ。勝利に向かって努力する人たちの姿を僕は否定しないけれど、「勝つ」ためになりふり構わない振る舞いには、なかなか共感することはできない。
もう少し時間が経てば「勝ち負け」という対立軸で語る問題でなくなっていくのだろうし(隈さんが『負ける建築』を出版したのは2004年だ)、いまも既に、より適した言葉が使われるようになってきている。「サステナビリティ」はその典型例だろう。
負けることに、もっと堂々としても良い。2番だって良い。1番だって良いけれど、3番手には3番手なりの存在感を示す余地がある。トップシェアが総取りという時代はとうに過ぎた。
本当のマジョリティは、マイノリティの総和なのだ。きっと。