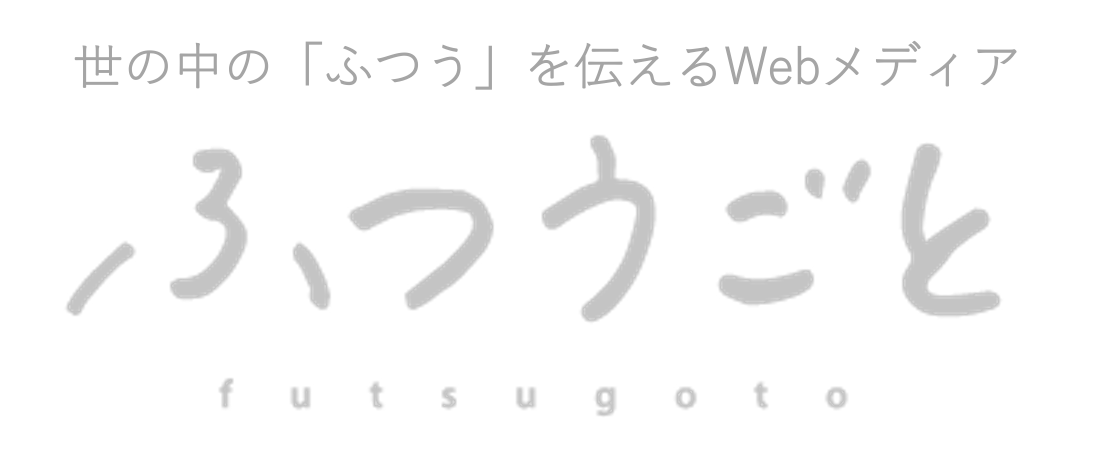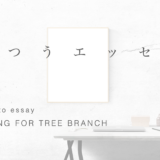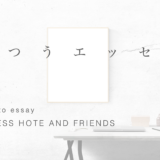その会話をした日の深夜、一人でドライブに出かけた。行き先は決めず、相手との今まで、今、これからに考えを巡らせた。当時住んでいた相模原から出て、車を止めたのは、秦野の菜の花台展望台だった。珍しくヤンキーの皆さんはいなかったので、もう深夜で街の明かりも消えて大してきれいではない夜景を見ながら、「どうでもいい」感覚を味わい、自分に残ったものは何か、心の隅々まで確認した。確認を続けると段々と、何も残っていないことが分かってくる。ないことを証明するのは難しいため、確認自体は終わらない。しかし、しばらく考えるうち、その状態に、何より自分が安心していることを発見した。次に、自分は安心した状態をポジティブに感じていると認知した時、ああ、これは、離婚しようと思った。愛が無くなると、相手に対して何も感じなくなるので、自分を優先することに罪悪感を持たなくなる。全く新しい発見だった。
これは、最近経験した、別のエピソードと対比するとよりわかりやすい。
岡山の実家の母は、昔から何につけても「あるべき姿」を持っているため、基本的に母の想定外の話を手順を踏まずに突然すると、受け入れてもらえず、あまり良いことがない。この「びっくりさせない」ことは、母とのコミュニケーションにおける基本プロトコルであり、年齢に応じて固執する傾向は強くなっていることも分かっていたはずなのに、つい最近、踏み外してしまった。
コロナ禍以降、孫たちを連れて帰省するのは年に1回となっていた。しかも、両親ともに後期高齢者の実家には、感染拡大防止の観点でも、子ども3人連れてお世話になる負担の面でも長期滞在ができず、特にここ2年、帰省の時は市内に宿を取っていた。今年、長男が小学校に上がった関係で、家族全員で移動できるのは、夏・冬・春の長期休みしか選択肢がなくなった。保育園は「休みますー」で何とかなったが、小学校にそういった気軽さはない。暦通りの休みは、7・5・4歳の子どもを連れて移動するにはなかなかにハードな環境で、お盆休みど真ん中とか、年末年始のラッシュはどうしても外したい。そのようなもろもろのスケジュールを来年3月まで見通すと、全員で帰省できるのは8月のお盆休み後か、春休みの数日しかない。であれば、どうせ実家滞在できないわけだし、感染リスクも少ないどこかの瀬戸内の島でワーケーションして、受入状況が許せば実家泊を増やそうかなという前のめりな計画を考えるに至った。だが、そのプランが固まったのは折悪しく酷暑が始まる6月下旬で、しかも私たちとしては然るべき検討プロセスを踏んでいたが、それは母に分かるはずも無かった。