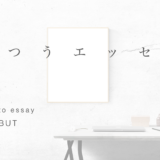友人や知人と久しぶりに会い、言葉を交わす。
それが飲みの席だったら、あっという間にラストオーダーになって。「いやあ、話が尽きなかったね」ということになる。場合によっては、もう1軒、お店をはしごするかもしれない。
お互いが、また会う日を願いながら別れる。当日の楽しさを噛み締めながら帰路に就くのは、人生のうちでも得難い幸せのひとつだ。
話が尽きない。
普段喋るのが苦手な人であっても、ある程度の年齢になっていれば「話が尽きない」ことを経験していない人はいないのではないか。もちろん関係性による。気心の知れた仲であれば、あれやこれやと話題が次から次へと展開されていく。
「しょーもない話するなよ!」と言われる恐れもない。つまり心理的安全性が保証されている状態なのだ。
そもそも、尽きないものの正体は何だろうか。
話術というか、話を展開するスキルというのは、人それぞれだ。
だから当然、相手の話を聞きながら退屈に思うこともある。だけど、話が尽きないという状態というのは、なんだかんだ話が尽きないのだから面白い。
つまり尽きないのは、話者ではなく、話の側に要因がありそうだ。
例えば、クワガタの話をするとして。
僕のクワガタに関する知識など、微々たるものだ。でも二人以上がクワガタを語るとき、話は一気に拡大していく。
僕はクワガタのことは知らなくても、クワガタの販売を通じて24歳でフェラーリを買った人の話は知っている。相手がそれを知らなければ、「え、それってどういうこと?」と話に乗ってくれるかもしれない。その話は「意外なことで商売が成立する」という、新たな方向へと展開するかもしれない。特定のビジネスに触れながら、その人の仕事観へと派生する可能性もある。
このように、ある話は、別の話と数珠繋ぎの関係にあるのだ。
話が尽きないのでなく、話というものが尽きないといった方が正確だ。それは人間の空想力も相まって、あらゆる方向へと膨らんでいく。
時間はあっという間に過ぎていくから、毎日そのような膨らみに付き合っていると「しんどい」と思えてしまうだろう。ほどほどが良い。
だけど、話というのは本来尽きないものなのだと思っていれば、「話す」ということのハードルが下がるように思える。自分が話すことが苦手でも、話そのものが尽きない構造になっているのだ。その構造を掴めさえすれば、そのコンプレックスは解消されていくのではないだろうか。
いやあ、ひとりで駄文を綴っていても、話が尽きそうにない。面白いかは、別にして……。