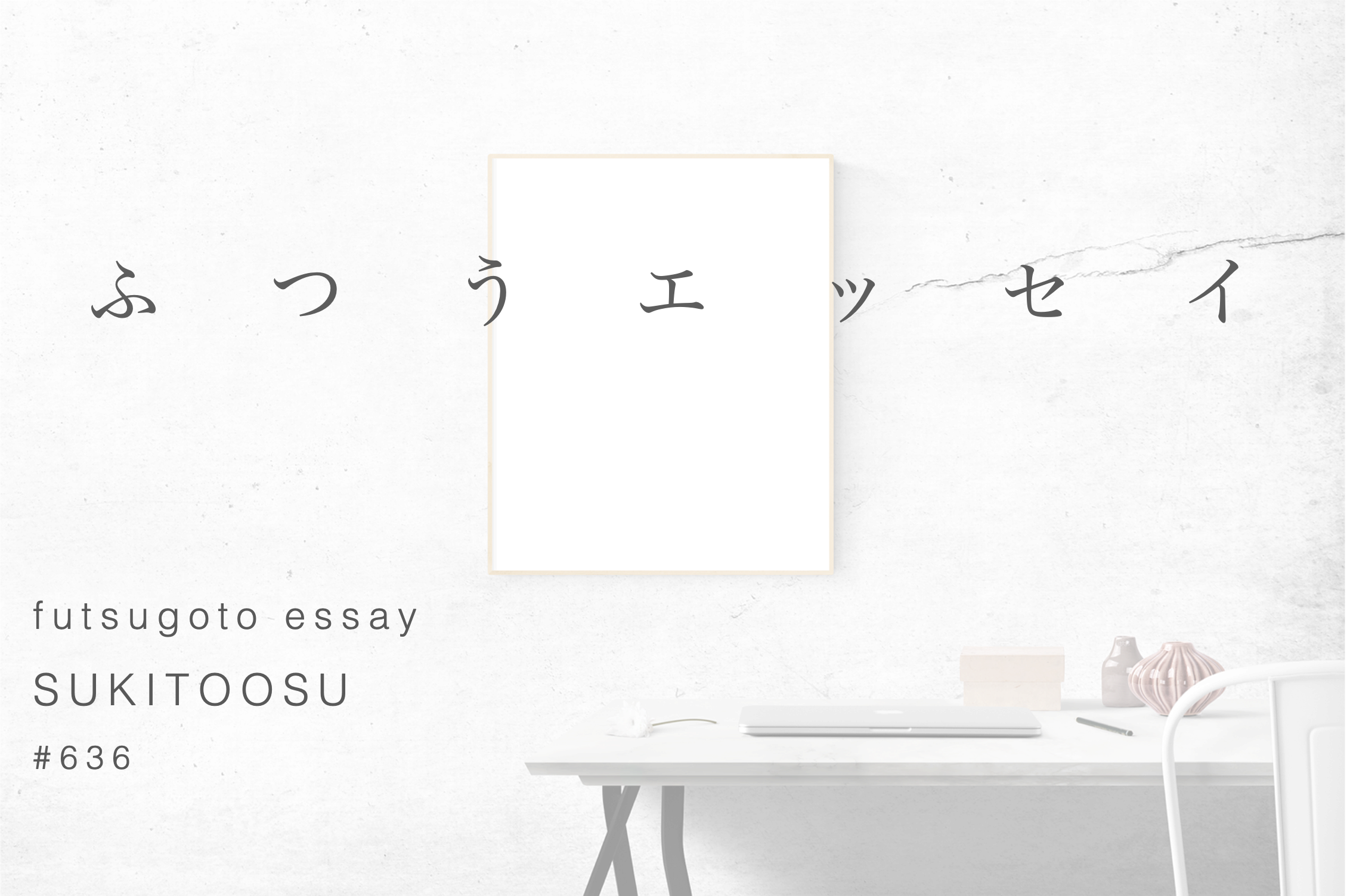思いがけない人がTwitterやnoteをやっていて、その内容をみて「ああ、こいつも人間なんだな」と思うことがある。
「こいつ」という言葉を使ったのは意図的で、察していただける通り「こいつ」に全く良いイメージは持っていないわけだ。フォローのひとつやふたつでもしてやろうかと思ったけれど、もちろん、そんなことはしない。記憶から消したい「あの日」というのは、僕にだってあるわけで、そこを無闇に掘り出したとしても傷つくだけだ。
誰かを殺してやりたいほど憎んだことは、今までない。だけど、人によっては「殺したいほど憎んでいる」という感覚を持っていても仕方ないと思っている。その感情に蓋をしようとするつもりはない。よほど辛いことがあったんだろう。僕にできることはほとんどないのだけど、その悔しさや憤りや怒りや悲しみが、別の形で報われたら良いなと思う。でも、そうやって無理やり別の形に転換してもらようなことは、僕は求めない。泣きたいときは泣けばいい。「ドライブ・マイ・カー」の家福のように。
「あの日」から、何年経っただろう。さて、僕自身は別の形に思いが変化しただろうか。それは分からない。でも、目の前の仕事がそこそこあって、期限を切りつつ待っていてくれる方がいる。ポックリ逝きたくはない。死ぬときは、多くの物事が空っぽの状態でいたい。「もっと生きたかった」と後悔するのは、良い。むしろ後悔くらい感じながら死んでいくのが本望だ。
あれもやりたかった、これもやりたかった。まあこれくらいでしゃーないやな。
そんな気持ちで、人生を終えたいと思う。