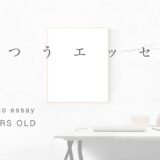子どもたちとの面会は、月に一度程度だが認められている。会うたび、まだ幼い次男は「帰りたくない」と泣く。ある程度の事情を把握している長男は、泣きじゃくる次男を見ては、うつむいて黙り込む。
「帰らないで」と、そう言って一緒に泣いてしまえたら、どれほど楽だろう。でも、私がそんなことをしたら、余計に彼らは辛くなる。
母親の傍にいることを子どもが望んでいたとしても、その発言ひとつで簡単に変更できるほど、親権制度は単純じゃない。一度定めた親権を変更するには、家庭裁判所に調停の申込みをしなければならない。弁護士を雇う場合、初期費用だけで30〜40万円はかかる。成功報酬まで含めると、少なくとも100万円ほどの支払いが発生する。ほしい権利を手にしたくとも、意志だけではどうにもできない。そんな理不尽は、世の中にいくらでも溢れている。
離婚当初から数ヶ月は、ただただ毎晩泣いていた。よくもこんなに涙が出るものだと我ながら感心するほど、声を上げて泣きじゃくった。
毎晩隣で寝ていた二人の坊主頭がいない。日に10回も20回も呼ばれていた「おかあさん」の声が聞こえない。連日の兄弟喧嘩に振り回されることも、反抗期の長男による許しがたい暴言に辟易とすることも、雨の日にまでねだられる外遊びの要求にうんざりさせられることも、なにも、ない。
ひとりの時間が増えてよかったじゃないか。
無理やりそう思おうとしては、毎日のように失敗していた。
私は前回のエッセイで、我が子が「大好き」なのに「離れたい」と感じる心理について綴った。でもそれは、あくまでも彼らの傍にいられる日常が続いていく日々を前提としたものだった。
月に一度しか息子たちに会えない。そんな毎日を、私は望んでなどいなかった。そういう意味の「離れたい」では、決してなかった。
散々泣いて、散々悔やんで、約束を守ってくれなかった元夫を憎み続けるのにも疲れた頃、季節は夏を迎えていた。離婚を機に引っ越した土地は、それまで住んでいた土地より、わずかに北に位置する。夏でもひんやりと冷たい朝晩の風を浴びながら、私はたびたび、海辺を散歩した。歩きながら、今の自分が「母親として」できることを考えた。そういう思考に至るまでに、ずいぶんと長い歳月を要した。