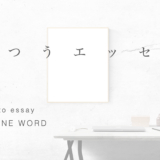ザ・ドリフターズの「いい湯だな」を、ときどき口ずさむ。
風呂に入ったときが一番多いのだが、自転車に乗っているときも、気付いたら口ずさんでいる。真冬の朝、風を裂くようにペダルを漕ぐ。温泉には程遠いシチュエーションなのに、気が付けば「いい、湯、だ、な」が口をつく。
これは、ザ・ドリフターズの歌が、日常に溶け込んでいるという証だ。
ドリフの世代でもなく、熱心に過去の曲を聴いているわけでもないのに、彼らの「いい湯だな」は広く知られている。鼻歌として、大勢の人に歌われている。
作家は、自ら書いた本が、読者の本棚に置かれている。
画家は、自ら描いた絵が、購入者の家やギャラリーに飾られている。
最初は特別な1冊であり、1枚だったものが、だんだんと日常性を高めていく。それは当たり前の存在でもあるし、ふとしたとき作品の良さに感動することでもある。
作家でも画家でもない僕が想像するのは難しいけれど、作品にとっては、美しい物語の渦中にいるような感覚ではないだろうか。
歌も同じだ。
毎年、実に多くの楽曲が発表されている。そのうちのいくつかはスマッシュヒットとなり、その年を象徴する曲として賞賛される。
けれど、どれだけ売れてかというのは、歌が日常性を帯びているかとは別問題だ。その年に売れたとしても、翌年には存在を忘れられることもある。逆にあまり売れなかったけれど、とある人にとっては代え難いほど大切な「1曲」として認識されることだってあるだろう。
その、数値換算できない思いは、すごく尊いものではないだろうか。
金持ちになって早期リタイアするよりも、ずっと仕事をして、誰かにとっての「1曲」的なものを生み出せる存在でありたい。