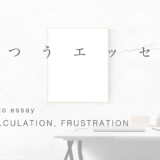コロナ禍で保育園行事は軒並み中止になっていたが、順調にいけば、息子の保育園では5月に遠足の予定があるらしい。
僕には、遠足の記憶があまり、ない。
昔の写真を振り返ると、どうやら動物園やら遊園地やらに行っているのだが、そこで楽しかったのかどうか記憶からすっぽりと抜け落ちている。
僕がかろうじて残っている遠足の記憶は、とある小学生の作文だ。読売新聞社が長く開催している全国小・中学校作文コンクールで優秀作品として表彰されたもので、30年前の作文の内容を憶えているのだ。(見ず知らずの他人の作文である)
・朝からみんなと一緒に遠足に出掛けた
・とても楽しかった
・弁当の時間、リュックサックの中にお弁当箱が入っていなかった
・いくら探してもない。バスにもなかった
・みんながお弁当からおかずを分けてくれた、美味しかった
・家に帰ると、お弁当箱がちょこんとテーブルに置いてあった
というのが、だいたいの筋だ。
特に、帰宅後のお弁当箱の「あり方」が印象に残っている。
本来であれば持参されるはずだった弁当箱。特に擬人化された表現でなかったように思うが、その弁当箱の悲哀というか、取り残されてしまった感が非常に切なく描かれていた。
遠足とは、楽しいものだ。
だけど、一部の人たちは「悲しい」思い出として残ってしまう。弁当を家に忘れてしまう人もいれば、ご飯を食べるときに弁当箱をひっくり返してしまった人もいるだろう。友達と喧嘩してしまったり、迷子になって心細い経験をしたりする人も、きっと存在する。
遠足という言葉も、楽しそうな文字で構成されていない。遠足とは「遠くに足をのばす」ということだが、つまりそれは、自分の安全が保証されている「近場」から離れることを意味する。
でも、親としては、子どもたちに楽しい思い出を持ってもらいたい。近いのも遠いのも、子どもにとっては掛け替えのない経験になるはずで、その経験をせっかくなら楽しい記憶で埋めてほしい。
そんなことを月曜日の朝に考えながら、はるか昔の、遠足の記憶をたどってみた。